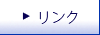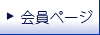活動報告
咸臨丸子孫の会の活動や関連の催しについて報告します。
★印は、会主催および会員対象の活動です。
★印は、会主催および会員対象の活動です。
2018年 ◎平成30年
| 9月17日 (月:祝) |
咸臨丸事件・壮士墓建立150年記念事業(静岡市)に参加
静岡市清水区の「次郎長翁を知る会」が主催した咸臨丸事件・壮士墓建立150年の記念事業に、子孫の会会員27名、関係者4名の計31名が参加しました。 午前中に清水港の壮士墓で営まれた咸臨丸殉難者供養祭では、藤本会長が子孫の会を代表して挨拶し、約80名の参列者が僧侶による読経のなか焼香して冥福を祈りました。 同日午後、清水テルサで開かれた記念講演会は180名定員の会場が満員の盛況で、子孫の会の尾駒眞理さんが立派な司会ぶりでした。 植松三十里さんの「咸臨丸清水港入港の顛末」、榎本隆光さんの「清水次郎長と榎本武揚」は素晴らしい講演でした(お二人とも子孫の会会員)。引き続き行われたトーク・セッションも勝海舟の子孫、高山みな子さんを迎えて大成功だったと思います。聴講の皆さんの反応もとても良く、講師のみなさんも話し易かったと言われました。 講演会の冒頭で藤本会長が挨拶し、長年にわたり壮士墓を守ってこられた次郎長翁を知る会に深い感謝の意を表しました。 この記念事業は、中日新聞・静岡新聞で報道されました(「報道記事」欄参照) [写真] ①壮士墓の供養祭であいさつする藤本会長 ②講演会で語る植松三十里さん ③トーク・セッション ④参加会員と関係者の集合写真 (①②③当会会員撮影、④するが企画観光局提供) |  ①  ②  ③  ④ |
|---|---|---|
| 9月11日(火) |
咸臨丸潜水調査の報告会(東京)に出席
9月7日~9日に北海道木古内町サラキ岬沖で、オランダ文化庁・東京海洋大学・NPO法人アジア水中考古学研究所(福岡)の合同調査チームによって咸臨丸遺物の潜水調査が実施されました(下記の見学記参照)。11日、東京虎ノ門のオランダ大使館においてその報告会が行われ、咸臨丸子孫の会の会長・幹事も出席しました。 オランダ文化庁の委託を受けたレオン・デルクセン氏より、今回の調査に至る経緯、調査対象の咸臨丸とそのオリジナル仕様、事前の調査、今回の潜水調査の活動とその結果についての基調報告があり、その後は自由討論が行われました。 今回の調査は3年計画の最終年にあたり、2017年1月のオランダ・日本における文献・資料調査、2017年11月の木古内町における現地調査をうけて、現地で潜水調査を行ったものです。 報告によれば、10年前に地元ダイバー吉田修一氏が泉沢の約500m沖合、深さ12~13mの海底で、長さ約20m、幅2~3mの木造船体を発見しています。今回、3日間で4回の潜水調査を行いましたが、この10年間で海底には土砂が堆積し、あまもが大量に繁茂繁殖していたため、今回使用したポールによる調査では発見に至らなかったとのことです。 調査チームは、あまもが枯れる2月から3月頃に、用具も検討して、再度潜水調査を行いたいとしています。 この潜水調査については、函館新聞・北海道新聞で報道されています(「報道記事」欄参照) | |
| 9月7日(金) ~9日(日) |
咸臨丸の潜水調査(木古内町)を見学
咸臨丸は明治4年(1871)9月、北海道木古内町サラキ岬沖で座礁・沈没しましたが、今回、オランダ文化庁、東京海洋大学、NPO法人アジア水中考古学研究所(福岡)の合同調査チームによって、その遺物を探索する潜水調査が行われました。 オランダのレオン・デルクセン氏、東京海洋大学の岩淵聡文教授が中心となって、地元ダイバーの吉田修一氏、アジア水中考古学研究所の林原利明さんらがサラキ岬沖で調査をしました。 5日の北海道の大規模な地震のため実施が心配されましたが、7日の午後1回、8日の午前、午後と各1回、9日の午前1回と計4回の潜水調査が行われました。 10年前に吉田さんがサラキ岬沖で20メートルくらいの木造船を発見、木の破片を採取したそうです。それを木古内町の役場に届けましたが、その後その破片は行方不明になっているそうです。 今回はその約20メートルの木造船体を探索しましたが、発見できませんでした。しかし存在するとしたら確実にこのポイントであろうという場所は確定できたそうです。 現在そこには海草が群生していて、ダイバーがその中に潜ることは危険でできませんでした。 来年の2月頃、その海草が枯れたところで再度潜水調査を行うということが検討されていました。 地元ダイバーの吉田さんが漁をしながら、海草の状況をみて東京海洋大学の岩淵教授と連絡を取り合い、また潜水調査を行うことを計画しています。 チームの調査活動は函館新聞・北海道新聞にも報道されました(「報道記事」をご参照ください) [写真] ①調査を終えて漁港に戻ってきた恵比寿丸 ②使用した道具を陸揚げするダイバーたち ③調査チームが結果を話し合う (当会会員撮影) |  ①  ②  ③ |
| 7月16日 (月:海の日) |
海舟フォーラム2018に参加
第15回勝海舟フォーラムが7月16日、東京墨田区のすみだリバーサイドホールで開催されました。 フォーラムに先立って、8時15分から銅像前で関係者による献花式が行われ、9時30分からフォーラムが開催されました。 まず勝海舟玄孫の高山みな子さん(咸臨丸子孫の会会員)による基調講演があり、続いて西郷隆盛曽孫の西郷吉太郎さんと高山さんによるパネルディスカッションが11時20分まで行われました。 江戸城無血開城の立役者とされる勝・西郷の子孫の登場に期待が集まったためか、700人収容のホールがほぼ満席になる人気でした。 高山さんの基調講演は短いながら中身の濃い熱弁でしたし、パネルデジスカッションも、おそらくお互いが初対面ではないことから、意気の合った楽しい内容でした。 咸臨丸子孫の会からは、高山さんを含めて6名が参加しました。 |  壇上の光景 |
| 6月16日(土) |
★講演会「幕府海軍」
東京四谷の主婦会館プラザエフにおいて、午後2時30分から、咸臨丸子孫の会の主催による「幕府海軍」の講演会が開催されました。咸臨丸子孫の会としては、2010年9月の万延元年遣米使節150周年記念事業以来の講演会となりました。 講演は2本立てで、まず金澤裕之氏(防衛省防衛研究所戦史研究センター所員)が「海軍の誕生——幕府海軍13年の航跡—−」と題して、ついで休憩をはさんで神谷大介氏(東海大学文学部非常勤講師)が「幕府海軍——幕末の浦賀と横須賀—−」と題して講演しました。 金澤氏は昨年5月に『幕府海軍の興亡』を上梓、神谷氏は今年『幕末の海軍 明治維新への航跡』を上梓するなど、現在お二人は幕末の海軍に関して最前線に立つ研究者です。その長年の研究成果の一端を聴講することができました。各講師の講演後にはそれぞれ活発な質疑応答が交わされ、予定の2時間を大幅に超過する熱心な会合となりました。 会場は、咸臨丸子孫の会会員22名をはじめ、幕末史関係団体の会員、研究者仲間の方々など、67人の聴講者で超満席の盛況でした。閉会後は場所を移して講師を囲む懇親会が開かれ、こちらも46人が集う盛会でした。 |  講演会風景  金澤裕之氏  質疑応答  神谷大介氏 |
| 5月12日(土) |
★木村家寄贈資料見学会
木村摂津守のご子孫が代々保存され、長く横浜開港資料館に寄託されていた資料が、昨年一括して同館へ寄贈されました。この木村喜毅・浩吉関係資料は一般公開されていますが、その一部をじっくり閲覧しました。 木村喜毅(芥舟)やブルック大尉のガラス板写真、咸臨丸で渡米時の英文名刺や小切手、自筆の自叙伝、福沢諭吉書簡、木村浩吉写真帖などを拝見しました。 木村忠昭さん(玄孫、横浜市在住)から、資料が戦災や戦後の接収の危機を乗り越えて横浜市鶴見の木村家の納戸に大切に保存されてきたこと、子ども時代に浩吉さん遺品の懐中時計を分解してしまったことなど、子ども時代から身近にあった資料のエピソードも披露されました。会員8名とその他1名が出席。 | |
| 4月28日(土) |
咸臨丸フェスティバルに参加
快晴に恵まれ、式典は横須賀市浦賀の旧住友重工浦賀工場レンガドック脇のテントで開催されました。来賓紹介では地元在住の咸臨丸乗組員の子孫(濱口興右衛門の曾孫)も紹介され、式典後は、オランダ大使館・アメリカ大使館関係者と交流しました。会員14名と会の関係者6名が出席しました。 今年は咸臨丸乗組員子孫と市民の交流の場は設けられなかったので、式典後は連れ立って咸臨丸出航の碑のある愛宕山公園や記念艦三笠など、横須賀市内の散策を楽しみました。 |  蘭・日・米の国旗がはためく会場で記念撮影 |
| 4月16日(月) |
徳川家臣団大会2018と講演会
静岡市葵区で4月16日、徳川みらい学会による2018年度徳川家臣団大会と本年度第1回講演会(静岡商工会議所、静岡市共催)が開催されました。幕臣の子孫など約500人が参集し、咸臨丸子孫の会からも15名が出席しました。 講演会では「明治維新150年と静岡」をテーマに、静岡とゆかりの深い山岡鉄舟に焦点を当てた朗読劇と講演が行われ、江戸城無血開城に大きな役割を果たした鉄舟の人物像に迫りました。 朗読劇は、俳優・奥野晃士氏が「鉄舟危機一発」と題して「歴史動読」を熱演しました。 講演では鉄舟が創始した全生庵(東京都台東区)の平井正修住職が、鉄舟の年譜をひもとき、その人となりから幕末明治期にかけての活躍を語りました。 | |
| 4月14日(土) |
★京都伏見の歴史散策
平戊辰戦争150周年を記念して、鳥羽伏見の戦いの伏見地区の戦跡を訪ねました。 2015年に開催した鳥羽伏見の戦いツアーの続き「伏見編」です。11時に近鉄・桃山御陵前駅に集合し、正井良治幹事の案内で16時まで、参加者7名でよく歩きました。 コースは明治天皇陵~乃木神社~薩摩軍大砲隊陣地~御香宮神社~魚三楼~伏見奉行所址地~月桂冠大倉記念館~土佐藩邸~伏見口の戦い激戦地~寺田屋でした。 時間の都合もあり、寺田屋から龍馬が逃走したルートは次の機会に譲り、京都駅近くで懇親会を行いました。 | |
| 3月18日(日) |
★咸臨丸子孫の会 第20回総会
平成30年度(2018)の総会が横浜市で開催され、全国から48名の会員が集まりました。 藤本増夫会長の開会挨拶ののち、例年通り、昨年度の活動報告・決算報告・会計監査・今年度の活動計画・予算案の各議案が諮られ、原案どおり承認されました。 その後、横浜中華街にて懇親会が開かれ、9月17日に開催予定の「咸臨丸事件・壮士墓建立150年記念事業」を主催する「次郎長翁を知る会」の副会長お二人を含む51名が参加、2時間あまり歓談しました。 |  懇親会風景 |